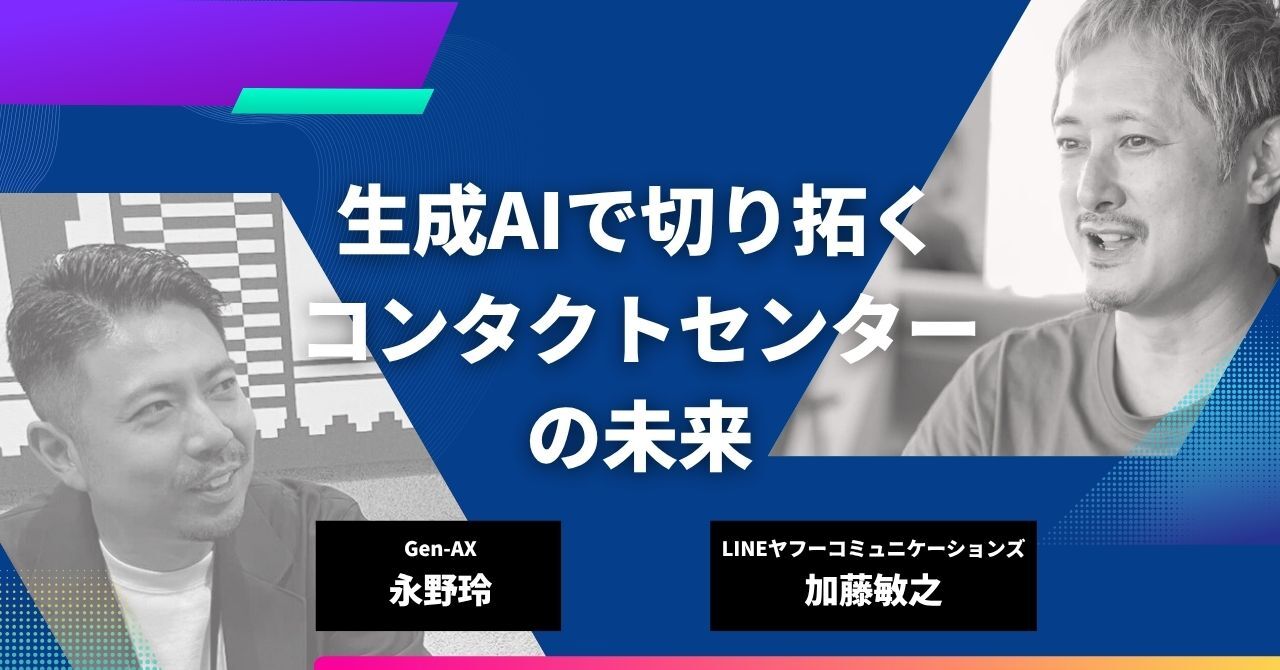生成AI活用率を半年で2倍に!オペレーター出身者が挑んだ推進の舞台裏
.jpg)
オペレーターから生成AI推進担当にキャリアチェンジしたAI推進チームの麓清紀さん。「業務の課題解決の糸口は、一番現場が理解している」という自身の経験から、現場と二人三脚で生成AI活用推進に取り組み、さまざまな施策によって半年で社内の生成AI活用率を2倍以上に引き上げました。
今回は、キャリアの道のりと生成AI推進の取り組み、その成果について伺いました。
麓 清紀
運営DX部 AI推進チーム
2019年 旧ヤフー株式会社に入社し、その後、PayPay株式会社に出向。審査業務を担当し、業務効率化チームに異動。2022年に旧LINE Fukuoka株式会社に入社。AIを中心とした各種DXツールの導入企画を担当。現在はAI推進チームでサービス運営現場の生成AIの活用推進を行っている。
2024年にLINEヤフーテックアカデミーで「文系出身でもリードできるAI推進方法」をテーマに登壇。
(アーカイブ動画:https://www.youtube.com/watch?v=6WmhJJDJE84)
オペレーターから生成AI推進担当へのキャリアチェンジ
―麓さんは、もともと旧ヤフー北九州センターの社員だったそうですね。
麓:はい。正確にはヤフーからPayPayへ出向し、加盟店の審査業務を担当していました。その業務の傍ら、独学で自動化やデータ分析を学び、効率化のアイデアを提案し続けた結果、業務改善チームへ異動することになったんです。そこでAIやRPAを活用した改善に携わりました。
その後はヤフーに帰任し、カスタマーサポート対応などを行っていましたが、やはりもっと業務改善に専念したいと考えていました。そんな時に旧LINE Fukuokaの募集を知り、応募することにしたんです。

―旧LINE Fukuokaに入社してからは、具体的にどのようなことをされているのですか?
麓:LINEスタンプ審査業務へのAI導入プロジェクトや、AIを使ったVOC(お客様の声)の分類など、運営業務効率化をメインで担当しています。
その他としては、弱視の方のパソコン作業をサポートする社内システムを企画しました。通常の読み上げツールでは画像内の文字が読み上げられないため、OCR技術(文字認識技術)と音声読み上げ技術を組み合わせて、画像内の文字も読み上げられるようにしました。
2023年にLINEヤフーグループに対話チャット型の独自AIアシスタントが導入されてからは、生成AIの活用推進に積極的に取り組んでいます。
半年で社内の生成AI活用率を2倍以上に導いた施策
―生成AIの活用推進に取り組み、わずか半年で社内活用率を2倍以上に引き上げられました。具体的にどのような施策を進めたのでしょうか?
麓:まずは、当社のコア事業である運営現場の社員に向けて、独自の生成AI研修を実施しました。研修動画の提供や、AI活用企画シートを使ったワークショップを実施し、この研修を通じて25件の新規AI企画が生まれ、そのうち11件が導入に向けてプロジェクト化されました。実際に導入された例としては、生成AIを使った文章の誤字脱字チェックや表記統一の自動化があり、これにより月約60時間の工数削減を実現しています。

―この研修によって順調に活用推進できたのでしょうか?
麓:いえ、課題もありました。セキュリティやシステム面のハードルが高く、社員アンケートでも「セキュリティへの不安」や「利用イメージの不足」が活用を妨げる要因だと分かりました。
そこで、まずは身近な業務効率化から取り組めるよう、生成AIへの心理的ハードルを下げる方針へとシフトしました。親会社であるLINEヤフーの生成AI統括本部と連携し、以下の施策を進めました。
・生成AIの基礎から応用まで、段階的に学べる研修コンテンツの制作・展開
・研修コンテンツの受講状況可視ツール開発・展開
・全社員向けに展開されているセキュリティ・ガバナンスのポータルページを、初心者でも分かる内容に刷新
・社内のプロンプト知見を共有する新プラットフォームの立ち上げ

▲生成AIへの心理的ハードルを下げるために、LINEヤフー生成AI統括本部と連携し様々なアクションを実施
こうした環境整備により、社員が生成AIに触れやすくなり、結果として社内の月間利用率は半年で2倍以上に増加しました。現在では、多くの社員が日常業務に生成AIを活用しています。

生成AIによって加速する組織成長と広がるキャリアパス
―社員にとって生成AIが身近になる活動もあり、現在は全社的に工数削減の目標数値を設定して生成AI活用を加速させていますね。運営業務においてどのように生成AIで効率化を進めていくのか、展望を教えてください。
麓:現場がよりが安心して生成AIを活用できるように、LINEヤフーコミュニケーションズ視点の生成AI利用ルールの整備や専用の相談窓口の設置に取り組んでいます。
並行して、部署横断でヒアリングを行い、生成AIと相性の良い業務を洗い出して、随時生成AIの導入を進めています。人間の手作業を前提としていた業務設計を生成AIに最適化していく作業も行っています。
私自身も業務に積極的に活用しており、企画の壁打ちやヒアリングのための質問リストの作成、要件の整理や資料のビジュアライズも生成AIに任せています。プロジェクトマネジメントにおける上流工程は、ある程度生成AIで対応できると実感しています。

―効率化することで、働き方にどのような変化が生まれましたか?
麓:定型的な業務を生成AIに任せることで、思考が必要な業務や新しいチャレンジに集中できるようになったと思います。私自身も、今までは月に1〜2本しか企画が作れなかったですが、今は月に5本以上も作れるようになり、現在、手元で動いているプロジェクトが2桁に達しています。AIによる情報処理スピードの加速と、人間が創造的なことに集中できるようになったことで、組織の成長スピードはこれまで以上に早くなっていくのではないでしょうか。サービス運営の現場では、オペレーターが持つノウハウを言語化して生成AIに学習させる作業や、生成AIの精度を高めるためのアノテーション作業、AI出力の評価・改善といった新しい業務が広がっています。
こうした取り組みを通じて強く感じるのは、生成AIを成果につなげるには、「課題や知識を引き出し、言語化する力」が欠かせない、ということです。
―生成AIの進化によって、プロンプトすらいずれ不要になるかもしれない、とも言われています。生成AI時代の中で、私たちはどのようなスキルを磨いていけば良いと思いますか?
麓:AIはデータがなければ動かないので、業務の中で感じている課題やナレッジを整理して伝える能力が求められます。現場でオペレーターが知識を言語化してAIに学習させているのも、その一例です。だからこそ、対人コミュニケーション能力を土台とした言語化の力が、生成AI時代に欠かせないスキルだと思います。